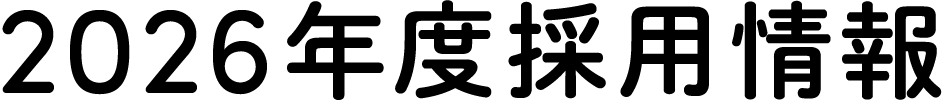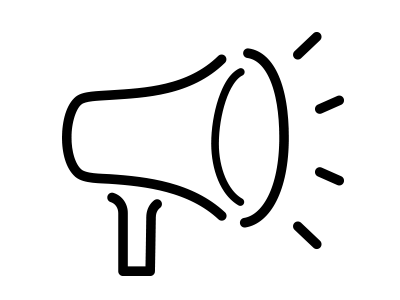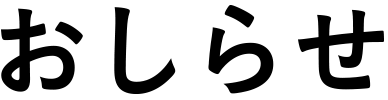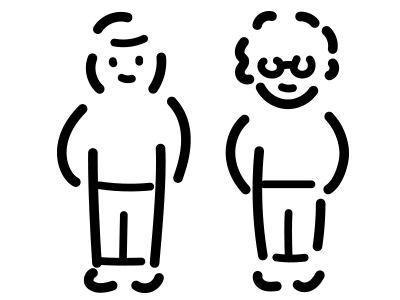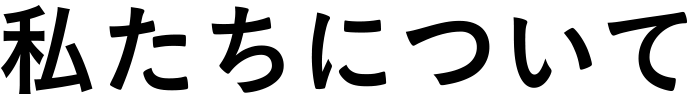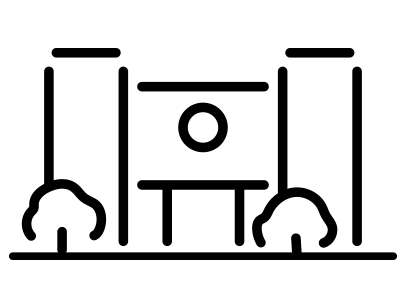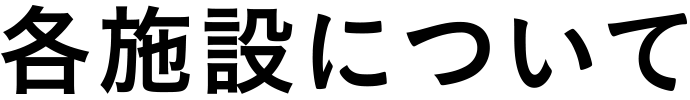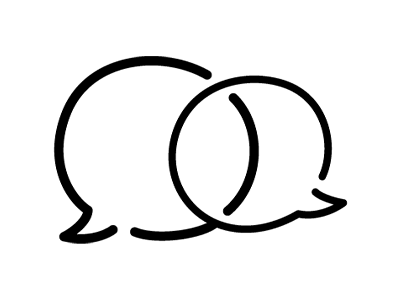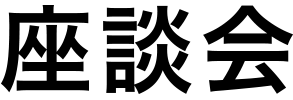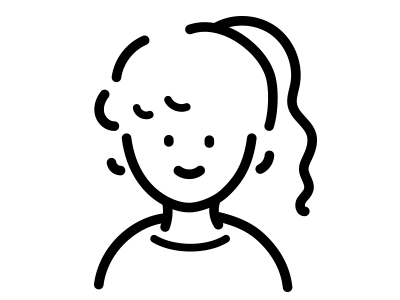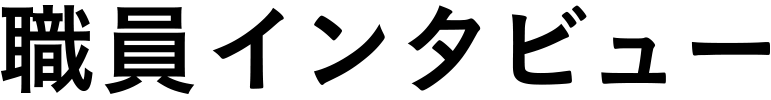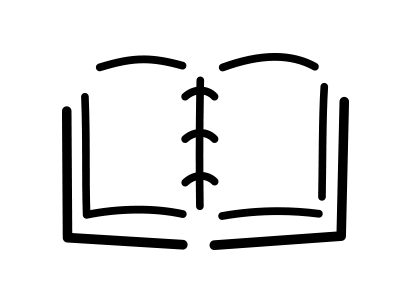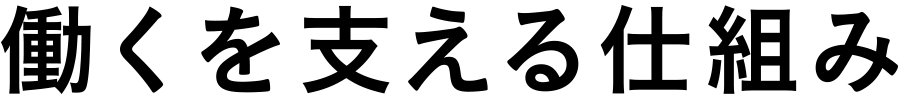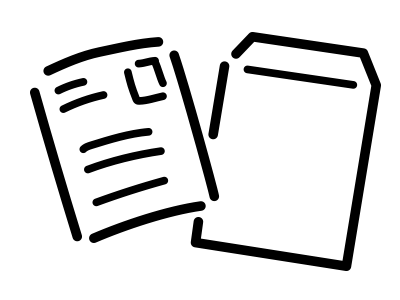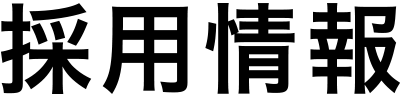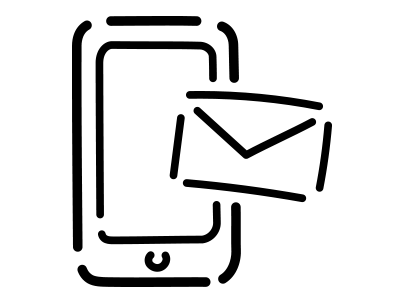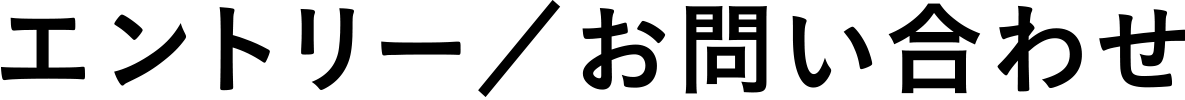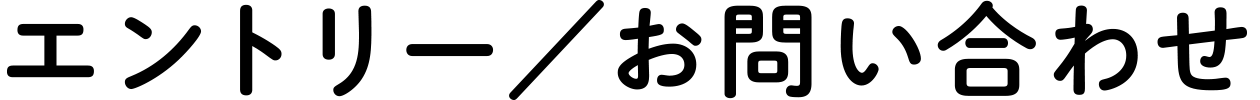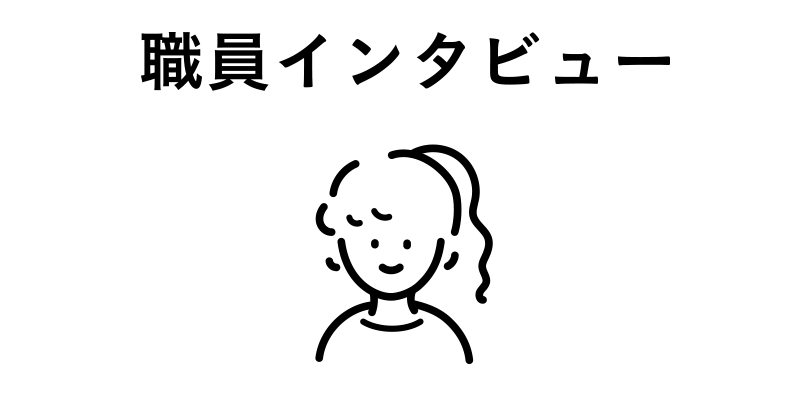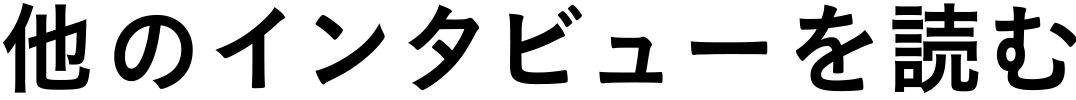書店員から福祉士の道へ。スキルを身に付けて自信が生まれました
大分県福祉会に入る前は、13年ほど書店員をしていました。しかし業界の将来に不安を感じ、最短で資格取得ができ働ける道を探したところ、福祉と出会い、その道に進みました。福祉の専門学校は高校卒業後すぐの人から50代まで、幅広い年代が通い、楽しい学校生活でした。今でもそのころの仲間と交流があり、ゴルフなどを一緒に楽しんでいます。1年で社会福祉士の資格を取得、精神的な分野にも興味があり、精神保健福祉士の資格も取得しました。そして専門学校で求人を見つけ、大分県福祉会に入社しました。入って4、5年は、目の前のことでせいいっぱいでしたね。
入職時は森の木の幼児ユニットで、未就学児の子どもを担当しました。何もかもが初めてで戸惑いばかりの毎日。夜中に飛び出していく子がいたり、子ども同士のトラブルを仲裁したり、四六時中目が離せないんです。大変さに入社1ヶ月くらいで、本気で辞めようかと悩んだほど。でも、森の木の先輩が様子を見たり声をかけてくれたり、心配して気にかけてくれたので助けられました。
森の木で身についたのは、子どもを寝かしつけるテクニック。一人ひとり、どうしたら眠りやすいかを把握して、徐々に対応できるようになりました。森の木の本園では、幼児ユニットに2年、男子ユニットに4年、家庭支援相談員(ファミリーソーシャルワーカー)として6年勤務しました。その後、大分市にある児童家庭支援センターのゆずりはに1年、そして2024年から佐伯市にある児童家庭支援センターHOPEでセンター長として勤務しています。私は、ソーシャルワーカーや児童家庭支援センターの相談業務など、専門職となってからは、専門的な内容に興味をもって自主的に勉強する機会が増えました。技術的にできることが増えると自信につながり、状況を冷静に捉え、余裕をもてるようになるようです。

しんどくても「腰を据えて待つ」姿勢が大切
森の木では行政で措置された子どもたちの支援を行っていましたが、現在のHOPEでは地域にある一般家庭の保護者から相談を受けています。相談者さんと話した後、必要に応じてほかの機関や施設につないだり、私たちで子どもを一時預かりしたりしています。大分県福祉会では、児童家庭支援センターが大分市とここ佐伯市の2ヶ所ありますが、佐伯市は相談を受ける事務所自体が、宿泊も可能な場所になっているので、相談者の方にすぐにお子さんの泊まりを含む一時預かりを提案しやすいのがよい点です。そうすると、相談員が子どもと一緒に過ごす時間も増え、直接接するからこそ感じることもあり、保護者にお伝えできることや相談時の言葉の説得力も変わってくるように感じています。
HOPEでは、24時間365日電話対応も行っています。例え深刻なことでも、じっくり耳を傾け、話を聴いています。相談内容はさまざまな環境や状況が関係していることもあり、話しをしてすぐに、適切な解決策を示せるわけではありません。でも、相談者さんが話すことで心の中を吐き出し、その後も長く付き合っていくうち、徐々に変化が訪れることもあります。話しながら自分で答えを見つける人もいるし、私たちが少し背中を押すこともできます。
この仕事で必要なのは、時間です。待つことって想像以上に疲れるし、しんどいですよ、正直。相談員としては手を尽くしきっても、そこから先はご本人次第で、見守るしかないときや、連絡がないまま「どうなったかなぁ」と想像することしかできないこともあり、もどかしいときも多々あります。そんなときは、腰を据えて待つことが大事です。待つためには、上司や周りの理解も必要不可欠。理解して待つこと、支援の共有が大切です。みんなで納得して進めていくしかないです。
信頼関係は、一緒に過ごした時間に比例します。側にいるだけでも意味があるんです。正解はわからないから、やるしかない。やみくもに手を出すだけなく、すぐには解決できないことを待つ姿勢が大切。今はそんなふうに感じています。
 ※記載内容は、2025年5月時点のものです。
※記載内容は、2025年5月時点のものです。
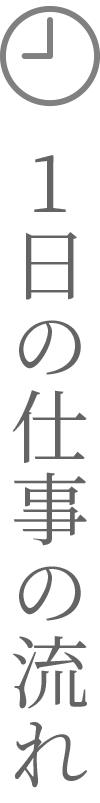 日勤
日勤
- 9時 出勤、引継ぎ、メール処理
- 10時 来所、面談対応
- 12時 昼食
- 14時 訪問
- 16時 来所、面談対応
- 17時 利用者、関係機関連絡、記録
- 18時 退勤